勤怠管理と入退室管理の連携は必要?メリットや注意点もあわせて解説!
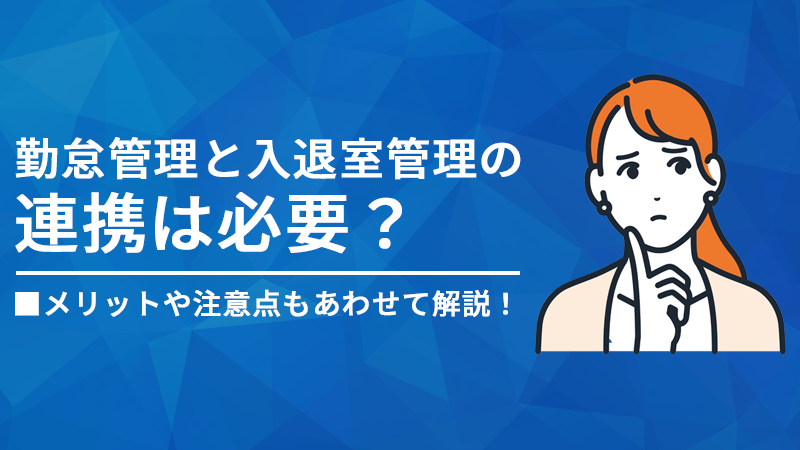
勤怠管理や入退室管理を手作業で行うと、手間がかかるうえにデータを改ざんされるリスクがあります。また、人的ミスが発生するリスクもあり、正確に従業員の勤務状況を把握できないことも考えられるでしょう。
こうした問題の解決に役立つのが、勤怠管理と入退室管理の連携です。この記事では、連携の必要性や連携によるメリットについて紹介します。連携時に注意すべきことも解説しますので、参考にしてください。
目次
1.勤怠管理と入退室管理の連携が必要な理由
連携が求められる理由は以下のとおりです。
- ・労働時間の把握が義務化
- ・サービス残業の防止
- ・カラ残業の防止
- ・上場の審査基準
それぞれの理由について解説します。
労働時間の把握が義務化
労働安全衛生法の改正により、企業は従業員の労働時間を客観的な方法で記録・管理することが求められるようになりました。過重労働による健康被害を防ぎ、適切な労務環境を整えるための措置です。
労働時間の記録方法として、以下の方法が推奨されています。
- ・タイムカードの打刻
- ・パソコンのログ取得
- ・入退室管理システムの活用
従来は自己申告に頼るケースが多く見られましたが、実態と異なる報告がなされる可能性があり、長時間労働の温床となる懸念がありました。そのため、より信頼性の高い記録方法の導入が求められています。
サービス残業の防止
従業員の適正な労働環境を守るためには、サービス残業を未然に防ぐ仕組みが必要です。従来の勤怠管理では、出退勤の記録をタイムカードやシステムの打刻に依存しているため、業務終了後もオフィスに残って実質的に残業していたケースが少なくありません。
このような状況を放置すると、長時間労働の常態化や企業の信頼低下につながるリスクがあります。とくに、上司の指示による強制的な残業や本人の意思による自主的な残業が問題視されています。
労働基準監督署の調査では、出退勤記録と実際の在室状況の整合性が厳しく確認されるため、適切な管理が求められます。入退室記録と勤怠データを一元化すれば、法令順守を徹底して労務トラブルを未然に防ぐことが可能です。
カラ残業の防止
業務がすでに終了しているにもかかわらず、私的な時間を過ごした後に退勤打刻するケースも考えられます。このような状況が常態化すると労働時間と実際の勤務状況に乖離が生じ、不要な残業代の支払いが発生する可能性があります。
たとえば、終業後に社内で雑談を続けたり、喫煙エリアで長時間過ごしたりした後に退勤を記録するなどの状況です。業務に従事していないにもかかわらず、残業時間として計上されることになり、企業にとって無駄な負担となります。
上場の審査基準
上場企業には財務の透明性が求められており、労働時間の適正な管理も審査対象のひとつです。労働基準法の遵守は必須事項であり、正確な出退勤記録の管理が行われていない場合、内部統制の不備と判断される可能性があります。
こうした課題を解決する手段として、入退室管理システムの導入が有効です。オフィスへの出入りを記録することで勤怠データとの整合性を確保し、不正な勤務申告や労働時間の過少・過大申告を防止できます。
こちらの記事では、入退室管理のシステムの選び方について解説しています。入退室管理の特徴や価格相場も取り上げているため、ぜひあわせてご覧ください。
2.労働時間を把握する方法
効果的な方法は以下の4つです。
- ・始業・終業時間の記録
- ・賃金台帳の記録
- ・自己申告制の対処
- ・書類の保存
それぞれの方法について解説します。
始業・終業時間の記録
適正な労働時間の管理を実現するには、1日の労働時間だけでなく、各従業員の始業時刻と終業時刻の正確な記録が不可欠です。労働時間の管理において、企業は客観的な方法を用いて労働時間を把握することが求められています。
具体的な記録方法として、上司や管理者が勤務状況を確認する手段があります。現場の実態を把握しやすい一方で、確認の手間がかかるため、すべての従業員に適用するのは難しいでしょう。
そのため、タイムカードやICカードを活用した記録方式がおすすめです。手間を減らすだけでなく、出退勤の打刻データを自動的に保存し、改ざんのリスクも防げます。
賃金台帳の記録
労働基準法第108条および同法施行規則第54条にもとづき、雇用主は従業員ごとに詳細な労働時間と賃金の記録を作成し、適切に管理する義務があります。記録には、以下の項目の記載が求められます。
- ・労働日数
- ・勤務時間
- ・休日出勤の有無
- ・時間外労働の時間数
- ・深夜勤務の状況
引用元:厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」
また、賃金台帳の適正な管理は労務トラブルの未然防止にもつながります。万が一、未払い賃金や違法な労働時間の管理が発覚した場合は企業の信用失墜だけでなく、法的な責任を問われる可能性があります。
たとえば、記録が不十分であったり虚偽の申告が行われた場合は、30万円以下の罰金が科されるリスクがあるため、注意が必要です。
自己申告制の対処

労働時間の管理において、客観的な記録を取得することが難しい場合、やむを得ず自己申告による方法が認められるケースがあります。しかし、例外的な措置であり、広く適用されるべきではありません。
また、自己申告制度を導入する際には、労働時間の正確性を担保するための十分な確認作業が不可欠です。申告内容の正当性を裏付けるために、上司による勤務実態の確認や、実際の業務量との整合性をチェックする仕組みが求められます。
加えて、申告された労働時間と、入退室記録やPCの使用履歴などの客観的なデータに差異がないかを定期的に検証することも欠かせません。手間を減らすためには、自己申告に頼るのではなく、可能な限り客観的な記録手段を導入するのが望ましいでしょう。
書類の保存
労働基準法第109条により、企業は労働者に関する各種書類を一定期間保管する義務があります。労働者の勤務状況や賃金に関する情報が含まれており、適切に管理すれば、労務トラブルを未然に防ぐことが可能です。
労働関係書類として保存が求められているのは、以下のとおりです。
- ・労働者名簿
- ・賃金台帳
- ・雇用に関する書類(契約書、労働条件通知書、履歴書など)
- ・解雇に関する書類(解雇通知書、予告手当の領収書など)
- ・災害補償関連の書類(診断書、補償支払い記録など)
- ・賃金関連の書類(昇給・減給通知、給与決定書など)
- ・その他の労働関係書類(出勤簿、タイムカード、残業命令書など)
3.勤怠管理と入退室管理を連携するメリット

連携するメリットは以下のとおりです。
- ・客観的な労働時間の把握
- ・勤怠管理業務の効率化
- ・セキュリティ強化
それぞれのメリットについて解説します。
客観的な労働時間の把握
従業員の勤務状況を客観的なデータで記録することが不可欠です。従来のタイムカードや自己申告による打刻方式では、実際の勤務時間と申告内容に乖離が生じることがあり、正確な労働時間の把握が困難でした。
とくに問題視されているのが、打刻後に業務を継続するサービス残業です。また、遅刻を隠すための不正な打刻なども発生する可能性があります。
このような課題を解決する手段として、入退室管理システムと勤怠管理システムの連携が有効です。オフィスの出入り時に自動的に打刻し、データを勤怠管理システムに直接反映させれば、勤務時間を正確に記録できるでしょう。
勤怠管理業務の効率化
従来のタイムカードや手作業による勤怠記録では、データの集計や確認作業に多くの時間がかかり、担当者の負担が増大していました。さらに、記録ミスや申告漏れが発生すると、労務管理の正確性が損なわれるリスクもあります。
その点、入退室管理と連携した勤怠システムを導入すれば、従業員が手動で打刻する必要がなくなります。アラート機能が備わっているシステムを活用すれば、残業時間の超過や勤怠不備をリアルタイムで通知できるため、管理者は迅速な対応が可能です。
また、システム化によって、データの集計や勤怠チェックが自動化されるため、人的コストの削減にもつながります。
セキュリティ強化
オフィスの安全性を高めるためには、入退室管理と勤怠管理を統合して不正アクセスを防ぐ仕組みを整えることが大切です。ICカードやスマートフォンアプリによる認証に加え、指紋や顔認証といった生体認証を取り入れれば、なりすましや無断侵入を防止できます。
また、入退室の履歴が自動で記録されるため、不審な行動の検知やアクセス制限の強化が可能です。特定の時間帯や部屋ごとにアクセス権限を設定して、機密情報の保護や関係者以外の立ち入りを制限できるのも利点です。
4.勤怠管理と入退室管理を連携する際の注意点

連携の際、以下4つのポイントに注意しましょう。
- ・システム導入に手間がかかる
- ・システムトラブルで記録できないリスクがある
- ・入退室者を特定できるシステムを選ぶ
- ・来客時や施錠トラブルへの対応
それぞれの注意点について解説します。
システム導入に手間がかかる
適切なシステムを導入し、運用環境を整備することが必要です。勤怠管理システムはクラウド型のサービスも多く比較的短期間で導入できますが、入退室管理システムの場合は専用の機器を設置する必要があるため、導入には一定の手間がかかります。
たとえば、ICカードリーダーや生体認証装置などのハードウェアを設置する際、オフィスのレイアウトや既存のセキュリティシステムとの互換性を考慮しなければなりません。また、工事をともなう場合、施工期間や費用の負担が発生する可能性もあります。
システムトラブルで記録できないリスクがある
入退室管理と勤怠管理を連携させると労働時間を正確に記録できますが、不具合による記録漏れのリスクも考慮しなければなりません。停電や通信障害、機器の故障などが発生した場合、入退室データが適切に取得されず、勤怠記録に欠落が生じる可能性があります。
とくに、システムを完全に自動化している場合、バックアップ体制が不十分だと、データが消失した際の復旧が難しくなります。こうしたリスクを軽減するためには、クラウド上でデータを保存できるシステムを選び、定期的なメンテナンスが欠かせません。
また、万が一トラブルが発生した際に迅速な対応ができるよう、サポート体制が整ったサービスを選ぶことも大切です。障害発生時の復旧手順を事前に確認し、システムが停止した場合の代替手段を用意しておきましょう。
入退室者を特定できるシステムを選ぶ
正確な勤怠管理のためには、個々の入退室記録を識別できるシステムを導入することが不可欠です。たとえば、暗証番号方式の入退室システムでは、同じコードを複数の従業員が使用する可能性があり、誰が出入りしたのかを特定するのが困難になります。
個人を特定できる仕組みとしては、ICカードや生体認証を活用したシステムが有効です。ICカードを使用すれば、従業員ごとの入退室履歴を記録でき、紛失時にはすぐに無効化できます。また、指紋や顔認証を取り入れれば、他人による不正利用を防ぐことも可能です。
来客時や施錠トラブルへの対応
オフィスの入退室管理を適切に運用するためには、来訪者対応や施錠トラブルへの備えも必要です。来客時にも訪問者の入退室履歴を記録すると、不正侵入やセキュリティ上のリスクを防げます。
また、従業員がセキュリティカードを忘れた場合や紛失した際にも、適切な対応が求められます。カードを一時的に貸与する場合は貸出記録を残し、返却時の管理を徹底しましょう。
とくに、紛失時には悪用のリスクがあるため、速やかに利用停止するといった対処が必要です。紛失トラブルに備えて、新しいカードを発行する体制を整えておくことも求められます。
5.入退室管理システムiDoorsの特徴

iDoorsは、企業のセキュリティ管理と業務効率化を図れる入退室管理システムです。多彩な認証方式を備えており、ICカードやQRコード認証に加え、顔認証やテンキー入力も利用可能です。企業の環境や運用方針に応じた柔軟なセキュリティ対策を実現できます。
また、二重認証やアンチパスバック機能により、不正入室の防止も可能です。オートロックやスケジュール解錠を活用すれば、従業員の利便性と安全性を両立できます。
さらに、複数拠点の一元管理や入退室ログの自動記録機能を搭載しており、管理業務にかかる負担の軽減も可能です。API連携機能も充実しており、既存の勤怠管理システムや予約システムとの統合もできます。
iDoorsでは、クラウドでドアセキュリティの管理をしています。多彩な認証方法やセキュリティ機能などに対応しています。ぜひあわせてご覧ください。
6.まとめ

勤怠管理と入退室管理の連携は、労働時間の適正な把握やセキュリティ強化に欠かせません。従来の自己申告やタイムカードの打刻だけでは、サービス残業やカラ残業といった問題を完全に防ぐことは困難です。
しかし、オフィスの入退室記録と勤怠データを一元化すれば、従業員の勤務実態を正確に管理し、不正な労働時間の申告を防止できます。ただし、システムの導入にあたっては、ハードウェアの設置や運用コスト、トラブル発生時の対応策などを十分に検討することが必要です。
iDoorsなら、勤怠管理システムとの連携はもちろん、遠隔拠点の一元管理やレンタルスペースの無人運営など、さまざまな課題を解決できます。生体認証によるなりすまし対策もできますので、オフィスのセキュリティ強化をご検討中の企業様は、ぜひiDoorsの導入をご検討ください。

